
賃貸物件の媒介契約(一般・専任・専任+管理)の違いやデメリット、選び方をプロが解説
賃貸経営において不動産会社をパートナーとして選ぶ際、入居者募 […]
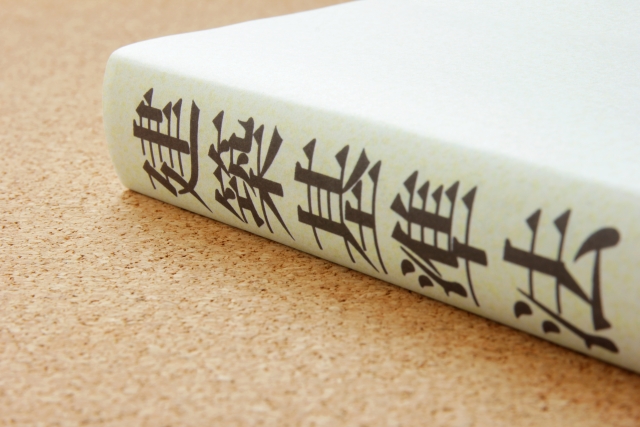
2025年4月の建築基準法改正により、木造建築物の新築や大規模リフォームの際に必要な手続きが増え、工期やコストに影響が出る可能性があります。特に、延べ面積200㎡を超える木造平屋の賃貸物件や、木造2階建ての戸建て賃貸、木造長屋(テラスハウス)、木造アパートを所有するオーナーにとっては、注意すべきポイントが多い改正です。
本記事では、エイブルが法改正の背景や具体的な影響、賃貸物件オーナーが注意すべき点についてわかりやすく解説します。
|
監修:株式会社エイブル 豊富な経験と専門知識を持つコンサルタントが多数在籍。建て替えやリフォームをはじめ、不動産の有効活用や資産運用に関するご相談に対し、最適なプランをご提案し、オーナー様を総合的にサポートしています。 エイブル 家主様・オーナー様向けサイト |
目次
2025年4月1日、建築基準法が改正され、木造建築物の建築確認手続きが見直されました。今回の改正の背景には、省エネ性能の向上と耐震性の強化という目的があります。
2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」などの改正により、すべての住宅・非住宅で省エネ基準適合が義務化されるとともに、地震や台風など自然災害への対策として、木造建築物の耐震基準が強化されることになりました。
この改正により、新築や大規模リフォームを行う際の建築確認手続きが厳格化され、オーナーの負担が増える可能性があります。
建築確認とは、新築・増築・改修を行う際に、建築基準法や関連法令に適合しているかを事前に審査し、確認を受ける手続きのことです。建築確認が認められなければ工事に着手できず、工事完了後も申請通りに施工されているかの検査が求められます。
これまでは、「4号特例」により、木造平屋建てや木造2階建ての建物の大規模リフォームでは建築確認が不要でした。しかし、今回の改正により、この特例が縮小され、より厳格な確認手続きが求められることになります。
エイブル:
確認手続きが厳格になるということは、オーナー様にとって手続きのプロセスが増えることを意味します。確認すべき点が増えるため、これまでより慎重な計画が求められるでしょう。そのため、オーナー様自身も情報をしっかりと把握し、対応可能な会社と連携することが重要です。
建築基準法では、建築物を規模や用途に応じて1号~4号建築物に分類しています。改正前の法律で2階建て以下の木造住宅などの「4号建築物」に該当していた小規模な木造建築物については、一定の条件を満たせば、建築士が設計することで審査の一部が省略される「4号特例」が適用されていました。しかし、2025年4月の建築基準法改正により、この特例の適用範囲が縮小され、より厳格な審査が求められるようになります。
エイブル:
今回の4号特例の改正は、建築業界に大きな影響を与えるものです。
オーナー様にとっても、リフォームや新築を計画する際に「この工事は新しい法律の影響を受けるのか」を事前に確認することが重要になります。これまで「4号建築物」は、建築確認の審査が一部省略されていました。
しかし、今回の改正により、多くの「4号建築物」が「新2号建築物」に移行し、審査が厳格化されることになります。特に新築では、確認審査にかかる期間が長くなるため、スケジュールの調整が必要になる可能性があります。
以下の建物は、法改正により新たに「新2号建築物」として扱われ、建築確認申請が厳格化されます。
・延べ面積200㎡を超える木造平屋の賃貸物件
・木造2階建ての戸建て賃貸物件、木造長屋(テラスハウス)、アパート
この変更により、工事の可否やコスト、工期に影響を受ける可能性があります。
一方で、延べ面積200㎡以下の木造平屋建ては、「新3号建築物」として扱われ、引き続き建築確認が必要な場合でも審査省略制度の対象になります。
2025年4月の法改正により、木造の平屋建て(延べ面積200㎡超)や木造2階建ての建築確認手続きが変更されます。これまでは、4号特例の適用により、建築士が設計すれば建築確認の一部審査が省略される仕組みでした。そのため、新築や大規模リフォームを行う際も、比較的スムーズに手続きを進めることができました。
しかし2025年4月以降、一定規模以上の木造建築物は「新2号建築物」に分類され、建築確認申請が必要になります。
エイブル:
今回の改正で特に影響が大きいのは新築の場合です。木造アパートの新築であれば、確認審査の期間が従来よりも必要になりますし、構造計算の義務化や省エネ基準の適合証明が求められるため、設計料や審査手数料が増額される可能性があります。
これまで建築確認が不要だった大規模リフォームも、今後は申請が必要になり、事前の準備やコスト負担が増える可能性があります。特に、建築確認の手続きが追加されることで、工事の着手までに時間がかかる点も注意すべきポイントです。スムーズな施工を行うためにも、事前のスケジュール調整や専門家への相談がより重要になります。
2025年4月の建築基準法改正により、大規模なリフォームでは建築確認が必要になるケースが増えます。ただし、すべてのリフォームが対象となるわけではなく、小規模な改修であれば、これまで通り確認申請なしで実施できます。
以下のような建物の構造に影響を与えないリフォームは、基本的に建築確認が不要です。
| ・クロスや床の貼り替え ・キッチン、トイレ、お風呂などの水回り設備の交換 ・バリアフリー化(手すりの設置やスロープの設置) ・構造上重要ではない間仕切壁の改修 ・屋根や外装の塗装 |
建物の主要構造部(壁・床・柱・梁・階段・屋根など)に影響を与える工事を行う場合、建築確認が必要になる可能性があります。これらの工事は、建物の安全性や耐震性に関わるため、改正後は建築確認申請が求められる可能性が高くなります。
| ・主要構造部(壁・床・柱・梁・階段・屋根)の50%を超える修繕工事 └ 床:床材(フローリングなど)を剥がして、改修範囲が根太まで及ぶ場合 └ 外壁:壁材(サイディングなど)を剥がして、柱を改修する場合 └ 屋根:屋根材を剥がして、垂木まで改修する場合 ・建物全体の間取りを変更するリフォーム ・フルリフォーム、スケルトンリフォーム |
【参考資料】リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)|国土交通省
【参考資料】床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて|国土交通省
エイブル:
今回の改正では、新築だけでなく「増築」や「大規模リフォーム」に関するルール変更も大きなポイントです。今まで申請しなくてよかったものも審査を受けなければならない形に変わるため、リフォームを計画する際には、リフォーム会社を通して確認申請が必要かどうかを事前に行政に確認することをお勧めします。
また、主要構造部の改修は建物全体の強度に大きく影響するため、確認申請の有無に関わらず、建築士に相談することをお勧めします。
一方で、以下のような特定の改修工事については、国土交通省より「大規模リフォームには該当しない」との見解が示されています。
| ・屋根ふき材のみの改修 ・カバー工法(既存の屋根や外壁の上に新しい材料をかぶせる改修) ・外壁の内側からの断熱改修 |
出典:屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて|国土交通省
今後法律が運用されていく中で、上記のように新たな緩和規定が設けられる可能性もあります。建築確認の要否を事前に確認し、スケジュールやコストへの影響を考慮した計画を立てることが重要です。
エイブル:
国としても、大規模リフォームによって耐震性能や断熱性能が向上することは望ましいと考えており、それに際して、違法な工事を防ぐためにも、確認申請を通じて安全な建物を維持する流れになっています。今後、具体的な事例が蓄積されることで、基準はさらに明確化されていくでしょう。
ただし、確認申請の必要性や手続きは物件によって異なります。適切な手続きを進めるためにも、建築士がいる工務店やリフォーム会社などの専門家に相談し、最新の情報をもとに対応を進めることをおすすめします。
2025年4月の法改正により、新築やリフォームの手続きが厳格化されました。これに伴い、工期の遅延やコスト増加の可能性があります。ここでは、特に注意すべきポイントを整理しました。
法改正により、建築確認申請が必要な範囲が広がることで、建築手続きにかかる期間が長くなる可能性があります。
建築確認の審査を行う自治体や指定確認検査機関の業務が増え、申請が集中することで審査に時間がかかるケースが予想されます。建築確認の許可が下りるまで工事は始められません。そのため、発注から施工完了までの期間が長くなり、従来よりも余裕をもったスケジュール管理が必要になります。
新築の場合、これまでより厳格な「建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適判)」を受ける必要があります。この審査も一定の期間を要するため、さらに工期が延びる可能性があります。
ただし、省エネ基準適合を使用基準で確認する場合や、住宅性能評価書を取得し、その写しを添付する場合は省エネ適判が不要になります。
確認申請図書や作成例については、下記をご参照ください。
【参考資料】改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請・審査マニュアル ダイジェスト版|国土交通省(P5「確認申請図書」一覧)
【参考資料】建築確認申請図書|(国土交通省)(P5「確認申請図書」一覧)
エイブル:
今回の改正では、確認申請にかかる期間が大幅に延びます。従来7日以内だった審査期間が35日以内になり、1ヶ月以上かかる可能性もあります。そのため、建築計画を立てる際は、従来よりも余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
築年数が経過している建物では、過去の建築図面が残っていないケースも少なくありません。図面がない場合、リフォームの前に建物調査を行い、新たに図面を作成する必要があります。この作業には調査費用や設計費用がかかるため、リフォーム費用が予想以上に高額になることも考えられます。
エイブル:
新築・リフォームどちらも、これまでより用意しなければならない書類が増えます。手続きが増え、結果的にコストの増加につながることを理解しておきましょう。
既存不適格建築物とは、現行の建築基準法に対し、法改正により適合しなくなっている状態の建物をさします。基本的には、大規模リフォームにあたって現行法規に適合させますが、リフォームの内容によっては緩和措置が使える可能性があります。お持ちの物件が既存不適格建築物であるとわかった場合は、建築士に相談しましょう。
また、再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしておらず、建物を建て替えることができない土地のことです。再建築不可物件の接道義務を満たすためには、以下のような対応が必要になる場合があります。
敷地を道路の中心線から2m以上後退させることで、接道義務を満たす(ただし、土地が狭くなるデメリットも)。
接道義務を満たすために隣接する土地を取得し、接道を確保する。接道義務を満たせない場合、大規模リフォーム自体が不可能になるケースもあります。
エイブル:
既存不適格建築物や再建築不可物件をお持ちのオーナー様は、事前に専門家へ相談し、どのような選択肢があるのかを把握することが大切です。
建築基準法の改正により、4号特例が縮小され、新築や大規模リフォームの手続きが厳格化されます。これに伴い、手間やコストは増えるものの、物件の安全性向上や資産価値の維持・向上につながる機会とも言えます。適切な建築やリフォームを行うことで、長期的に競争力のある賃貸経営を実現できるでしょう。
リフォームを検討する際は、「この工事に確認申請が必要か?」を事前に確認し、信頼できる業者と連携することが重要です。法令を遵守するだけでなく、物件の魅力を高める視点を持つことで、将来にわたって安定した賃貸経営を続けることができます。
エイブル:
リフォームについては、壁紙の貼り替えや、設備機器の交換などは、これまでどおり確認申請不要なので、過度に心配する必要はありません。ただし、将来を見据えて大規模リフォームや間取り変更を考えているのであれば、確認申請の有無に関わらず、建築士や建築士の在籍するリフォーム会社に相談することをお勧めします。
エイブルでは、オーナー様が安心して賃貸経営を続けられるよう、賃貸物件のリフォーム・新築に関するご相談を無料で受け付けています。「リフォームを検討しているけど、法改正の影響を受けるの?」「木造アパートの建て替えにどれくらいの期間がかかる?」といった疑問を抱えるオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。